歴史の片隅にひっそりと佇む遊郭という世界を想像すると、僕は時折、不思議な気持ちになります。まるで古い絵巻物の中から、遊女たちの姿が静かに立ち上がってくるような感じです。
僕は歴史の専門家ではないし、偉そうに語れる立場ではありません。でも語らずにはいれません。
というのも、なぜか、遊女という存在には、人間の本質がにじみ出ているような気がしているからです。
最初に断っておきますが、遊女たちは多くの場合、自ら望んでその世界に足を踏み入れたわけではありません。むしろ、家族の事情や貧困といった現実によって、否応なくその場所に追い込まれていった人たちがほとんどだったのでしょう。
でも、そんな彼女たちがその中で見せた強さ、そして賢さは、単に「可哀想な人たち」なんて言葉で片付けられるものではありません。
そんな立場の彼女たちですが、僕が驚かされるのは、遊女たちが持っていた『現実を冷静に見つめる力』です。過酷な環境の中でも、自分の置かれた状況をきちんと理解し、その中でどう生き抜くかを考え抜いていました。
何かを諦めながら、でも完全には希望を手放さないような・・・そんな絶妙なバランス感覚。それはもはや、サバイバル能力と呼んでも良いかもしれません。
特に僕が密かに惹かれているのが、彼女たちの「建前」の使い方です。現代の僕たちは「本音で生きよう」とか「建前は偽《いつわ」りだ」なんて、耳障りの良い言葉で、他人より自分が大事だという価値観を信じようとしています。
遊女たちは、常に笑顔を絶やさず、お客にやさしく接し、従順な振る舞いを求められていました。もちろん、それが本心であるとは限りません。でも、その演技を通じて、自分の身を守り、少しでも良い立場を手に入れようとしていたのです。それって、とてもしたたかで、強い生き方だと思いませんか。
むしろ僕は、そうした「建前」の中にこそ、人間の深い知性や強さが表れているように感じています。本心をすべてさらけ出せばラクかもしれません。でも、それをあえて隠し、社会の中で生き抜いていくという選択にも、確かな尊さがあるのではないでしょうか。
また、遊女たちは数奇の目にも晒される立場でした。でも、同じ境遇の中で生きる仲間たちと、支え合い、時には競い合いながら、複雑な人間関係を築いていました。その中で培われた連帯感や社会性は、現代社会の人間関係、特に職場やSNSなどにも通じる部分があります。
もちろん、そんな彼女たちの適応力の高さが、過酷な現実を正当化するものではありません。やはり、多くの遊女たちは自由を奪われ、不本意な状況に置かれていた存在です。そのことを忘れてはなりません。
でも、そんな中でも彼女たちは、「本心」を失わずに生きていたのです。本当は自由が欲しい、普通の人生を歩みたかった・・・そんな気持ちをどこかに抱えながらも、目の前の現実に対応していた。僕は、その内面の強さこそ、もっとも学ぶべき部分だと思っています。
彼女たちは日々、心の葛藤を抱えていました。笑顔の裏には、僕たちの想像を超える精神的疲労があったはずです。
建前を続けるということは、自分を消耗することでもあります。それでも仮面をかぶり続けた彼女たちの姿には、計り知れない強さと哀しみが滲み出ています。
そしてふと、現代の僕たちに目を向けると・・・僕たちもまた、いろんな建前に囲まれて生きています。会社の中での立ち振る舞い、SNSでの見せ方、家族や友人との距離感などなど・・・。本音を完全にさらけ出せる場なんて、案外ありません。
でも、それを嘆いても仕方がありません。むしろ、建前の中でいかに自分を保ち、時に楽しみながら生きていけるか。それこそが、現代人に必要な力です。
遊女たちは、極限の状況下でその術を身につけていました。だからこそ、彼女たちの生き様は、現代を生きる僕たちのヒントを与えてくれるのです。
最後にお伝えしたいのは、遊女たちの物語が決して「過去だけの話」ではないということです。本心と建前の間で揺れながら、それでも自分を見失わずに生きようとする人たちは、今の時代にもたくさんいます。僕自身もそのひとりです。
社会で生活を送る上で、他人との関わりを断つことは不可能です。だからこそ「本音」だけではなく、「建前」を武器にしたたかに生きる。あなたの「本心」を守るためには、従順なフリで相手を欺す必要もある。
彼女たちの生き方は、現代を生きる僕たちにとっての「警鐘」であり、同時に「希望」でもあるのではないでしょうか。
(了)
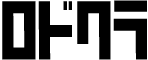



コメント