自由気ままで自己中心的・・・常識で考えれば集団行動を求められる現代社会では周りから浮いてしまい、生きづらいハズなのに、なぜか周囲に助けられ、苦労もせず困難を乗り越える人間を見て理解に苦しんだ経験はありませんか。
偉い訳でも、能力が高い訳でもなく、どちらかと言うと欠点だらけの人間なのに、困っていると周囲が放っておかず、助けてしまう・・・常識や協調性といった社会生活の前提からすれば、彼らは扱いづらい存在であり、敬遠されるはずです。ですが現実には、そんな「ワガママな自由人」がなぜか好かれいるんですよね。
この現象は、人間という存在の奥深さ、そして現代社会における人間性の在り方そのものを映し出しているのではないでしょうか。
彼らはまるで、現代人が日々の生活の中で忘れかけている「ある種の真理」を生きているのです。つまり、これは単なる性格分析ではありません。
我々人間が、どのように人間らしく生きるかという、哲学的な問いなのかもしれません。
素直であることは「非効率」か?

現代社会は、効率と成果を重視する構造で成り立っています。ビジネスの世界では「空気を読む」ことが求められ、SNSでは「バズる」ための戦略が日々練られています。
そこにおいて、人間関係すらも「計算の対象」として扱われがちです。「この発言をするとどう思われるか」「好印象を残すにはどうすべきか」といった意識が、私たちのふるまいを決定しています。
そんな中にあって、自由人はあまりに異質です。彼らは「嫌いなものは嫌い」「欲しいものは欲しい」と、思ったことをそのまま言葉にしています。他者との関係においても、損得や上下関係に敏感であるどころか、まるで気にかけていません。現代の社会通念では、これは「非効率」「KY」「自己中心的」と評されるハズです。
つまり、文明・科学が進むにつれて人は自然な自分を見失い、他者の目を過度に意識するようになります。本来なら「素直であること」は、本来の人間性であるはずなのに、現代社会では、むしろ、非効率的な振る舞いとして扱われるようになっているのです。
なのに、自由人が放つ率直さや無邪気さが人を惹きつけるのはなぜか?
それは、現代人の誰もが心のどこかで「演技をやめたい」「本音で生きたい」と願っているからではないでしょうか。
「失敗を恐れない人間」と「失敗が許されない社会」
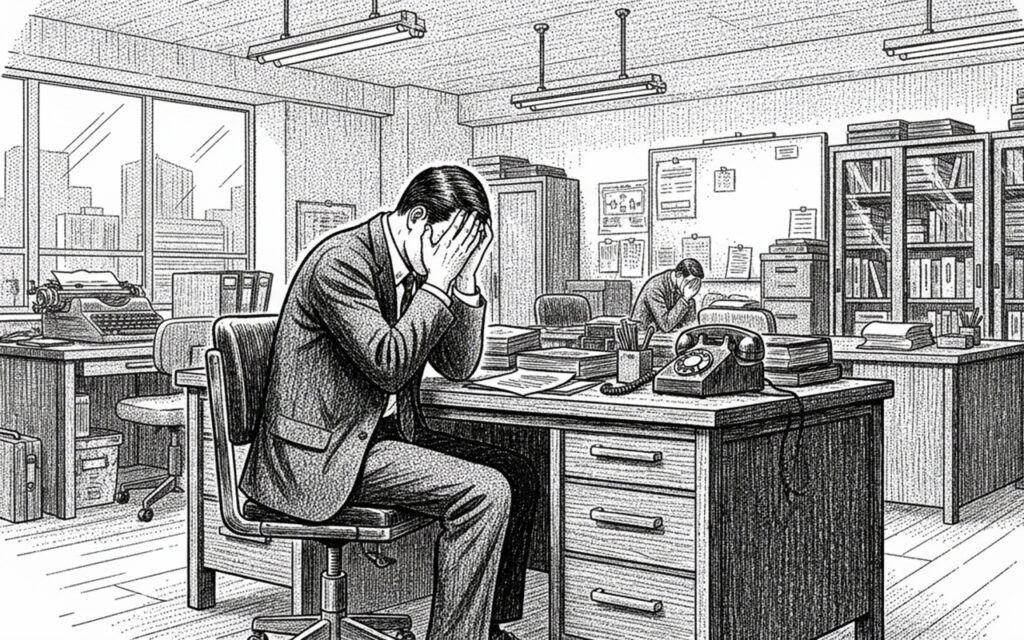
現代は、いわゆる「失敗に厳しい社会」です。炎上リスク、コンプライアンス、評価経済、自己責任論・・・ありとあらゆる文脈が、人々に「間違うことへの恐れ」を植え付けています。ちょっとした発言がSNSで袋叩きにされ、キャリアの綻びが人生全体を左右します。そんな緊張感のなかで、多くの人は自分を抑え込みながら生きているのが現実です。
それに対し、自由人はあまりに呑気に見える・・・「まあ、なんとかなるでしょ」と笑い、しょっちゅう失敗し、トラブルに巻き込まれながらも、それを深刻には捉えていません。まるで、間違えることすら楽しんでいるかのようです。
自由人は、「真に強いものは、変化や失敗に耐えるのではなく、それらによって強くなる」と考えています。彼らは、計画通りに進まないことを前提にしながらも、それを恐れていません。むしろ、そこにこそ生きる実感があるとさえ感じているように見えます。
一方で、現代人は「失敗しないための予防線」を張り巡らせ、人生のあらゆる局面を過剰に恐れています。自由人は、その「過剰な安全装置」に対するアンチテーゼであり、だからこそ人々の心に引っかかるのです。
演じない人間の力──「安心」とは何か?

社会心理学では、人間関係には「心理的安全性」が必要だとされています。これは、「自分の意見を言っても否定されない」「間違っても受け入れてもらえる」という空気のこと。
だけど、現実の社会では、常にその安全性が保証されているわけではありません。むしろ、評価され、比較され、品定めされることのほうが多いのではないでしょうか。
でも、自由人のそばにいると、多くの人が「この人の前では無理をしなくていい」と感じます。なぜなら、彼ら自身が「演じていない」から。他人によく思われようとしないし、自分を良く見せようともしません。その飾らなさが、逆説的に他者に安心感を与えるのです。
他人に嫌われる人間の多くは、相手をモノとして扱い、機能的な関係にとどまります。ですが、自由人は、相手を「かけがえのない存在」として尊重しているのです。自由人は、お互いを尊敬する関係を自然と生み出す力を持っています。つまり、彼らは「本当の人と人が出会う瞬間」を作り出しているのです。
「余白」を与える存在──秩序に対する異議申し立て
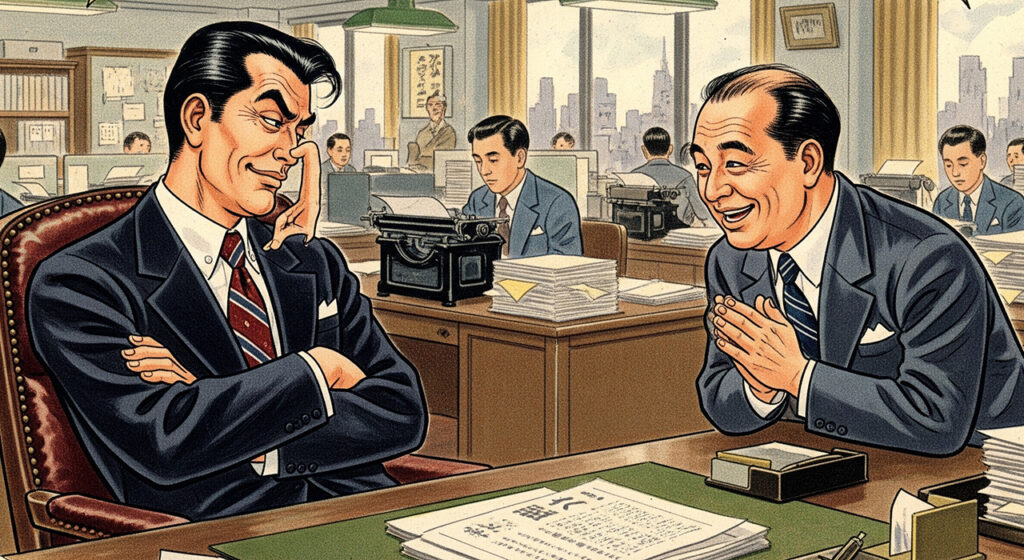
現代社会は、「正解」や「最適解」を求める傾向が強い傾向があります。教育も、仕事も、恋愛でさえも、「どうすれば正解に近づけるか」という思考が支配しています。そして、その思考は他者に対する寛容さを奪っていきます。「こうすべきなのに、あの人はできていない」といった批判が、誰の中にも少なからず潜んでいるんです。
そんな中で、自由人のような人物が現れると、彼らの「常識外れな言動」が周囲に衝撃を与えます。それは時に迷惑であり、混乱をもたらします。ですが、同時に、彼らは「正しさの枠」を崩すことによって、他者に「余白」を与えます。
「正しくあらねばならない」と自分を追い込んでいた人が、自由人の言動によってふと緩み、「ああ、自分も少し肩の力を抜いていいんだ」と思えます。それこそが、彼らの持つ最大の社会的役割かもしれません。彼らは「秩序の破壊者」であると同時に、「癒しの媒介者」でもあるのです。
不完全で魅力的な人間に、人は惹かれる

最終的に、人は「完璧な人間」に感動するのではなく、「不完全でも魅力的な人間」に心を動かされます。不完全さは、共感を生むのです。「あの人もダメなところがある」「それでもあんなに愛されている」・・・この事実が、人間にとってどれほど救いになるか想像してみてください。
完璧さは距離を生み、不完全さは親密さを生みます。自由人が愛されるのは、彼らが人間の「欠け」を隠さないからです。そしてその「欠け」は、人間性の一部であり、私たち自身が抑えつけてきた部分です。
自然体であることの美学

自由気ままで自己中心的、けれどどこか愛おしい・・・そんな人間は、私たちが日々の社会生活の中で見失っている「自然体の人間らしさ」を体現しているのかもしれません。
彼らは、正解や効率を求める社会のルールの外側にいます。ですがその存在は、逆説的に、私たちが「本当に大切にすべきこと」を思い出させてくれます。
計算ではなく感情で動くこと。失敗を恐れずに挑戦すること。仮面を外し、素直な自分でいること。
それは決して、簡単なことではありません。だからこそ、自由人は稀であり、価値があるのです。彼らのような存在が、現代という閉塞した社会において、一筋の風穴を開けてくれるのではないでしょうか。
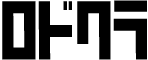
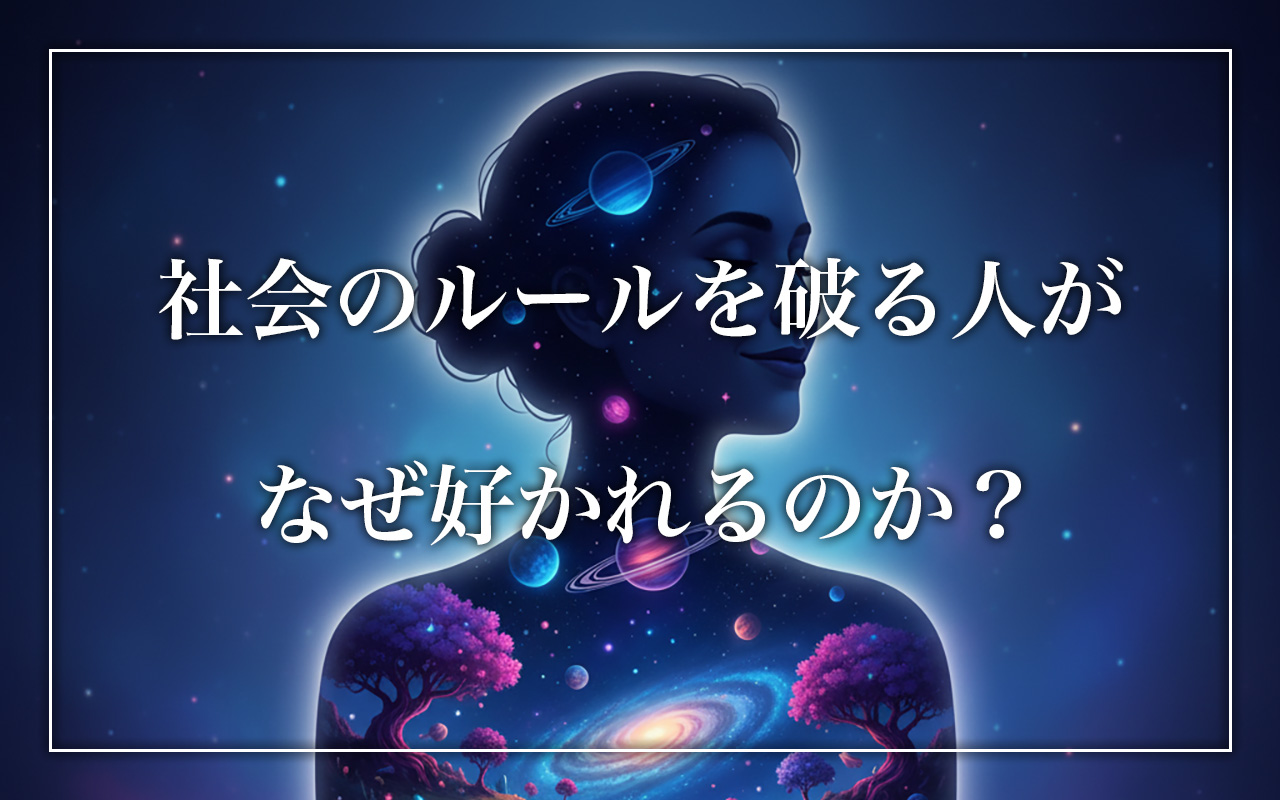


コメント