人間というものは、実に不思議な反応を示す生き物である。

どういうこと?
例えば、誰かに自分の意見を正されただけで、まるで存在そのものを否定されたかのように騒ぎ立てる人間がいる。
こちらとしては単に事実を指摘したに過ぎず、何ら人格を攻撃するつもりもないのだが、そうした人間は「侮辱された」とばかりに声を荒げる。

面倒くさい・・・
正直にいえば、僕はその種の人間が大嫌いである。だが嫌悪感の奥に、どうにも歴史的・心理的な事情が潜んでいるようにも思われる。
自己肯定感と「自分は正しい」の混同

心理学でいうところの「自己肯定感」は、文字どおり「自分の存在そのものに価値がある」と受け止められる心の基盤を指す。ところが、しばしば人はこれを「自分の判断は常に正しい」と勘違いする。

勘違い甚だしい・・・
両者は似て非なるものである。自己肯定感の強い人間は、むしろ間違いを指摘されても動じない。「私は誤っていた」と冷静に受け入れても、自分の価値そのものが損なわれるわけではないからである。
反対に、自己肯定感の弱い人間は、ちょっとした反論を「自分の存在否定」と受け取り、過剰に反発する。

いるね・・・
ここには心理学でいう「認知的不協和」が働いている。自分の中で「正しい」と信じていたものが揺らぐと、人は強い不快を覚える。そ
の不快感を消し去るために、反論した相手を攻撃する。つまり論点はすでに消え失せ、ただ感情の処理だけが目的化してしまうのである。
行動経済学に見る人間の反応

行動経済学の世界では、人間がいかに非合理であるかが数々の実験によって証明されてきた。

そうなの?
例えば「損失回避バイアス」。人は利益を得る喜びよりも、損失を被る痛みを数倍も大きく感じる。
自分の意見を否定されると、人はそれを「心の財産を失った」かのように感じる。実際には何ひとつ失っていないのに、である。だから必死に守ろうとする。その必死さがワーワー騒ぐ姿となって現れる。

面倒くさい・・・
さらに「確証バイアス」も無視できない。人は自分に都合のよい情報ばかりを集め、耳の痛い事実は排除する傾向がある。
そこへ他者からの指摘が飛び込めば、これはもう大事件だ。バイアスを崩されまいと、反射的に攻撃に出る。これが議論の場を荒らす。
哲学における対話と誤解

古代ギリシアに生きたソクラテスは、問答を通じて相手の思考を深め、真理へと導こうとした。彼にとって反論は否定ではなく、むしろ共に歩む道程であった。

哲学・・・
ところが現代社会では、意見がそのままアイデンティティと結びついてしまっている。意見を否定されることは、自分の存在を突き崩されることに等しい、と受け止めてしまうのだ。

人格と意見は別
これは哲学の伝統からすれば、大きな誤解である。
東洋思想においては「無我」や「調和」が重んじられ、意見の対立そのものを「自己否定」とみなす発想はあまり強くなかった。
意見はあくまで流れる水のようなもの、状況に応じて変化し得るものとして扱われた。したがって、反論に過剰反応する姿は、むしろ近代的個人主義が生んだ病ともいえる。
どうしてそうした人間が増えたのか
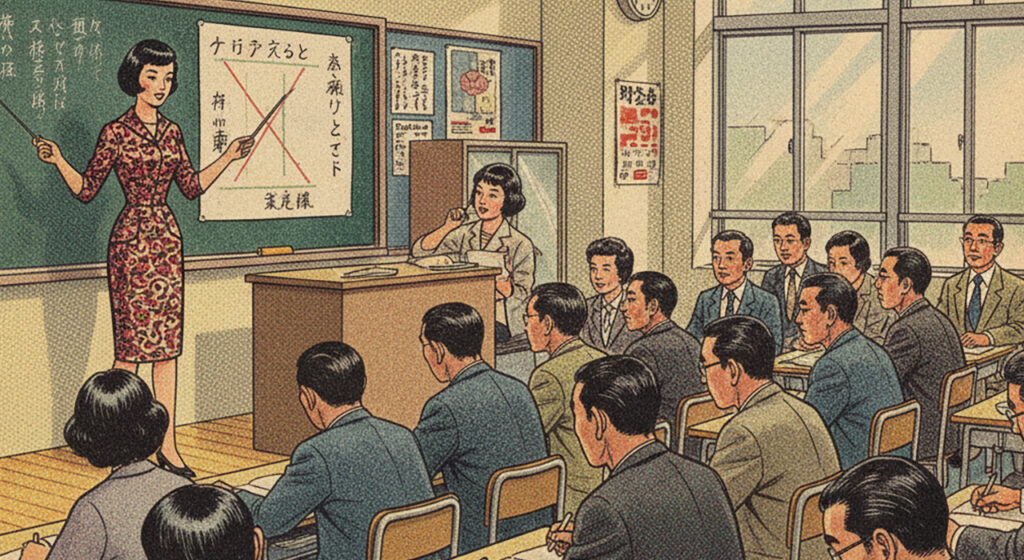
ここで、なぜこの種の人間が現代において増えたのかを考えてみたい。
まず、「自己肯定感を高めよ」という言説が社会に氾濫したことがある。
本来それは「存在そのものを受け入れる」ための概念だったのに「意見や判断は常に尊重されるべきだ」と曲解された。その誤解が、指摘を即座に「存在否定」と読み替える人々を育てた。
第二に、近代以降の個人主義がある。
「自分らしさを大事にせよ」という価値観は、尊い理念である反面、「自分の意見=自分そのもの」という短絡を生んだ。そこへSNSが拍車をかけた。
いいねの数やフォロワーは、いまや人間の小さな勲章である。だから否定的なコメントは、ただの意見ではなく「自分を消し去る脅威」と映る。
第三に、教育の影響もある。戦後日本の学校は「減点方式」で、誤りを「糧」ではなく「恥」として刷り込んできた。大人になっても誤りを突かれると動揺し、恥をかかされたと感じる。これが過剰反応を助長している。
最後に、歴史的な権威の失墜がある。かつては師や親方の叱責を当然のものと受け止めたが、民主主義は「誰もが平等である」と説いた。その理念の影で「誰にも意見を否定されてはならない」という妙な感覚が育った。
人は他者を権威として認めない代わりに、自分自身を小さな権威として守りに走るようになったのである。
まとめに代えて

こうして見てみると、人が指摘を否定と取り違えて騒ぎ立てるのは、単なる「未熟さ」だけでは説明できない。
心理学的な防衛反応、経済学的なバイアス、哲学的な誤解、そして近代史の流れが複雑に絡み合った結果である。そして何より、現代の社会環境が、そうした人間を増殖させている。

面倒くさい・・・
僕は依然としてその種の人間が嫌いだ。だが、もはやそれは個人の性格の問題というよりも、近代社会が抱え込んだ宿痾なのだろう。
もっとも、この考察そのものがまた誰かの「存在否定」と受け取られ、ワーワー騒がれるのかもしれない。人間というのは、時代が進歩してもなお、可笑しみと厄介さを失わない生き物なのである。
(了)
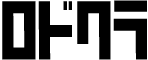



コメント