茨城県に住んでいない人からすると、茨城県民はみんな同じように見えるかもしれない。
でも、実際は、県内でも地域によって人々の性格や文化はまったく違う。特に南北では、まるで違う人種のように感じられるほどだ。
長い間、県北と県南は互いに交流が少なく、文化も言葉も異なってきた。僕は、この「どちらが本当の茨城らしいか」という考え方の違いを、いわば、茨城県の南北問題として捉えている。
県北:古き良き茨城
僕の地元である県北(茨城県人はけんぽくと呼ぶ)は、人口が減り、過疎化が進んでいる地域だ。昔は日立製作所を中心とした街として栄えたが、近年は活気が失われつつある。
この地域には昔ながらの茨城の文化が残っている。特に、茨城を象徴する茨城弁が日常的に使われており、幼い子どもたちも当たり前のように話している。
県南:東京に近い新しい茨城
一方、県南は東京のベッドタウンとして発展している。つくば学園都市のような新しい街もあり、東京に近いことから、県北を「田舎」だと見る人も少なくない。
県南では、東京からの移住者が多いためか、もともと住んでいる人でも茨城弁を話す人が少ない。中には、茨城弁を「恥ずかしい」と感じる人もいる。彼らにとって東京は身近な存在で、つくばエクスプレスを使えばすぐに都心に行けるため、半分東京人のような感覚を持っている人も多い。
南北問題は幻だった?
こうして見ると、県北と県南はまったく違うように感じられる。県北の人々が思う「本当の茨城らしさ」と、県南の人々が思う「茨城らしさ」は違う。僕は、標準語を話す県南の人々を、半分東京人であるという意味を込めて“エセ茨城人”と表現することもある。
しかし、この話を地元の友人にしてみたところ、「へ〜、そうなの?」といったあっさりした反応が返ってきた。もしかしたら、茨城県民は地元へのこだわりや誇りをあまり強く持たない、おおらかな人が多いのかもしれない。南北問題というのは、実は僕の考えすぎだったのかもしれない。
人口が減っていく地域と、東京のベッドタウンとして発展していく地域。この二つの顔を持つことこそ、今の茨城の魅力なのかもしれない。
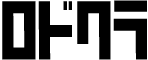


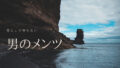
コメント