水戸には、昔から「三ぽい」という言葉がある。

どういうこと?

茨城の県民性である
人生の第一次ステージを茨城で過ごした僕のアイデンティティの本質は、この「三ぽい」からきているのかもしれない・・・。「三ぽい」とは
理屈っぽい。怒りっぽい。骨っぽい。

骨っぽい?
初めて聞くと、なんだか扱いづらそうな性格に思えるかもしれない。でも、水戸の歴史をひも解くと、その気質が生まれた必然性が見えてくる。
この気質は形を変えながら今も受け継がれており、茨城県内の他の地域にも、それぞれの歴史や地理に根ざした独自の気質がある。

ほう、聞こうじゃないか
水戸人の「理屈っぽさ」― 水戸学の遺産

水戸人が理屈っぽいと言われる背景には、水戸藩が担ってきた歴史的役割がある。徳川御三家として、幕府を補佐するだけでなく「なぜ幕府が存在するのか」「日本のあるべき姿とは何か」を深く問い続けたのが水戸藩だった。

幕府を支えるために・・・
この探求を支えたのが水戸学だ。二代藩主の徳川光圀は『大日本史』の編纂を命じ、日本の歴史を通して「正統」とは何かを追究させた。学問を重んじる気風は弘道館へと受け継がれ、藩士たちは幼い頃から「筋道を立てて物事を論じる」訓練を積んだのである。

そうなんだね
この気質は現代にも残っている。会議や議論の場で、水戸出身者は「根拠は?」「筋は通ってる?」と問いかけることを好む。これは周りから見ると「理屈っぽい」と感じられるかもしれないが、その根底には「道理を重んじる」という気質があるのだ。
水戸人の「怒りっぽさ」― 尊王攘夷の炎

「怒りっぽい」という評価は、幕末の水戸藩を思い浮かべると納得できる。

日本を守るために・・・
水戸は尊王攘夷運動の先駆者であり、多くの志士を輩出した。1860年の桜田門外の変で大老・井伊直弼を討った浪士の多くは水戸藩士だった。彼らは、安政の大獄で尊皇派が弾圧されたことに義憤を抱き、命を懸けて行動したのだ。
水戸の「怒りっぽさ」は、単なる短気や激情とは違う。それは義理や正義に反することへの激しい拒絶の姿勢だ。

筋を通す姿勢だね
この気質は今も息づいている。職場や地域社会で不正や不合理に直面すると、茨城出身者は黙っていない。東京に住んでいても、水戸の人が「それは違うでしょ」とはっきり口にする場面を目にすることがある。そこには、幕末の志士たちを動かした「義の炎」が流れている。
水戸人の「骨っぽさ」― 誠実と責任の気質

三ぽいの最後は「骨っぽい」だ。骨っぽいとは、気骨がある性格(正しいと信じたことを、いかなる困難にも屈せず、貫き通す強い意志や気概を持っている)をいう。

正義を守るために・・・
これは最もポジティブに捉えられるべき気質だろう。
水戸藩は財政難や内紛に苦しみながらも、「忠義」と「学問」を支えに藩を維持し続けた。その中で人々は「筋を曲げず、責任を果たす」という姿勢を身につけた。

頑固そう・・・
現代の茨城県民も、不器用なほどに誠実だ。例え、損をしても義理を通し、約束を守る。時に「頑固で扱いづらい」と思われるかもしれないが、いざという時、決して裏切らない。まさに「骨っぽい」と呼ぶにふさわしい人柄なのだ。
現代に残る「三ぽい」の影

この三ぽいは、現代でも形を変えて残っている。
東京で「茨城出身」と言うと、決まって「納豆の県ね」と言われる。しかし、水戸人の誇りは納豆より、この「三ぽい」にあるのだ。
茨城県地域の気質とその背景
ちなみに、茨城県は広大で、地域ごとに異なる気質がある。それぞれのルーツを探ると、歴史や地理の必然が見えてくる。
つくば人 ― 理系インテリの冷静さ

つくばは近代以降、研究学園都市として発展した。
筑波大学をはじめとする研究機関に全国から人が集まり、理系的で合理的な気質が育まれた。
水戸の「理屈っぽさ」が伝統的な筋論なら、つくばのそれは科学的合理性に基づいている。
県北人 ― 技術者の誇り
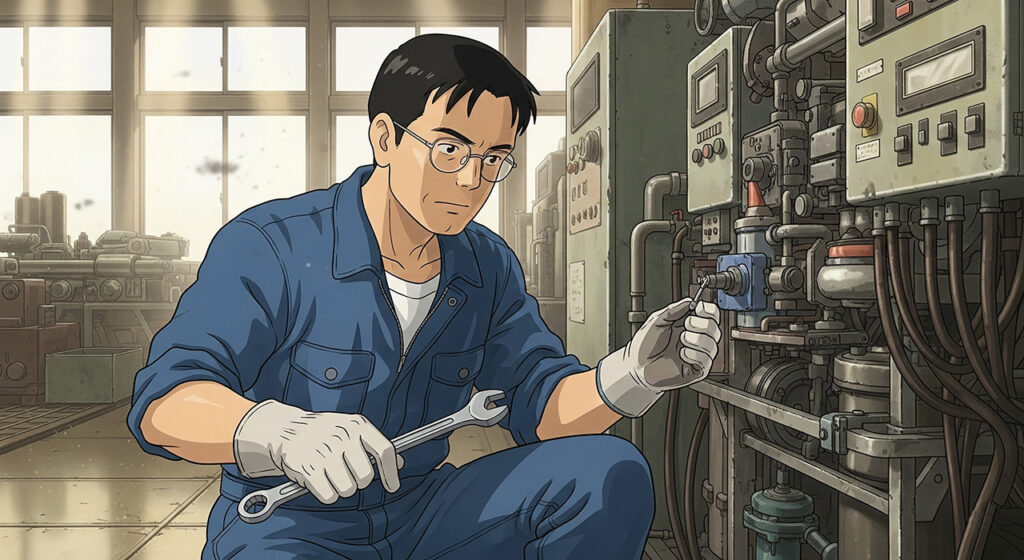
県北には日立市があり、日立製作所の城下町として知られる。産業と共に発展したこの地域では、勤勉で真面目な職人気質を持つ人が多い。
実直さは企業文化そのものだ。
高度成長期を支えた技術者たちの矜持が、今も人々の気質に刻まれている。
鹿島人 ― 豪快な仲間意識

鹿島神宮という古代からの信仰と、鹿島港を中心とした漁業・港湾の歴史が人々を豪快にした。
鹿島アントラーズの熱狂的なサポーター文化に象徴されるように、祭りやスポーツを愛し、仲間意識が強い。
海に面した土地柄が、人を開放的にし、裏表のない性格を育んだ。
県西人 ― 商都の現実主義

古河や結城は江戸との往来が盛んで、結城紬などの交易を通じて発展した。
商人が多かったため、合理的で現実的な気質が育まれた。水戸人が筋を通すのに対し、県西人は柔軟に立ち回る。
世渡り上手なのは歴史の必然だ。
県南人 ― 東京志向の都会的気質

土浦や取手などは江戸・東京との結びつきが強く、文化や流行をいち早く取り入れてきた。
都会的で柔らかく、よそ者を受け入れる土壌がある。茨城の中でも比較的「東京寄り」の空気をまとっているのが県南人だ。
歴史に見る「三ぽい」の体現者

水戸人の三ぽいを語る上で、やはり桜田門外の変の浪士たちは象徴的だ。彼らは理屈を尽くして討幕の正義を論じ、義憤に駆られて行動を起こし、命を懸けて筋を通した。
まさに「理屈っぽく」「怒りっぽく」「骨っぽい」気質の体現者だった。
現代に目を移すと、水戸出身の著名人にも三ぽいの影を見ることができる。

決して怒っていない・・・
もちろん、彼らが意識して「三ぽい」を体現しているわけではない。しかし、水戸で育ったことで培われた気質が、どこかに滲み出ているのは確かだ。
最後に

水戸人は、理屈っぽく、怒りっぽく、骨っぽい。
三ぽいは短所に見えるかもしれないが、実は誇るべき資質なのだ。
茨城県は広く、つくばの理知もあれば、日立の実直さもある。鹿行の豪快さもあれば、県西のしたたかさもある。だが、その中でも水戸の三ぽいは、歴史の重みを背負った象徴的な気質だ。
東京の雑踏の中で「茨城出身です」と話せば、まずは納豆の話になる。だが、僕が他県の人に胸を張って語りたいのは納豆ではない。水戸人の三ぽいだ。
理屈を通し、義に憤り、筋を曲げない。

僕のアイデンティティだ!!
それこそが、僕の故郷・水戸の人々の誇りであり、茨城という土地の骨格なのだ。
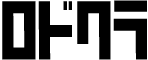
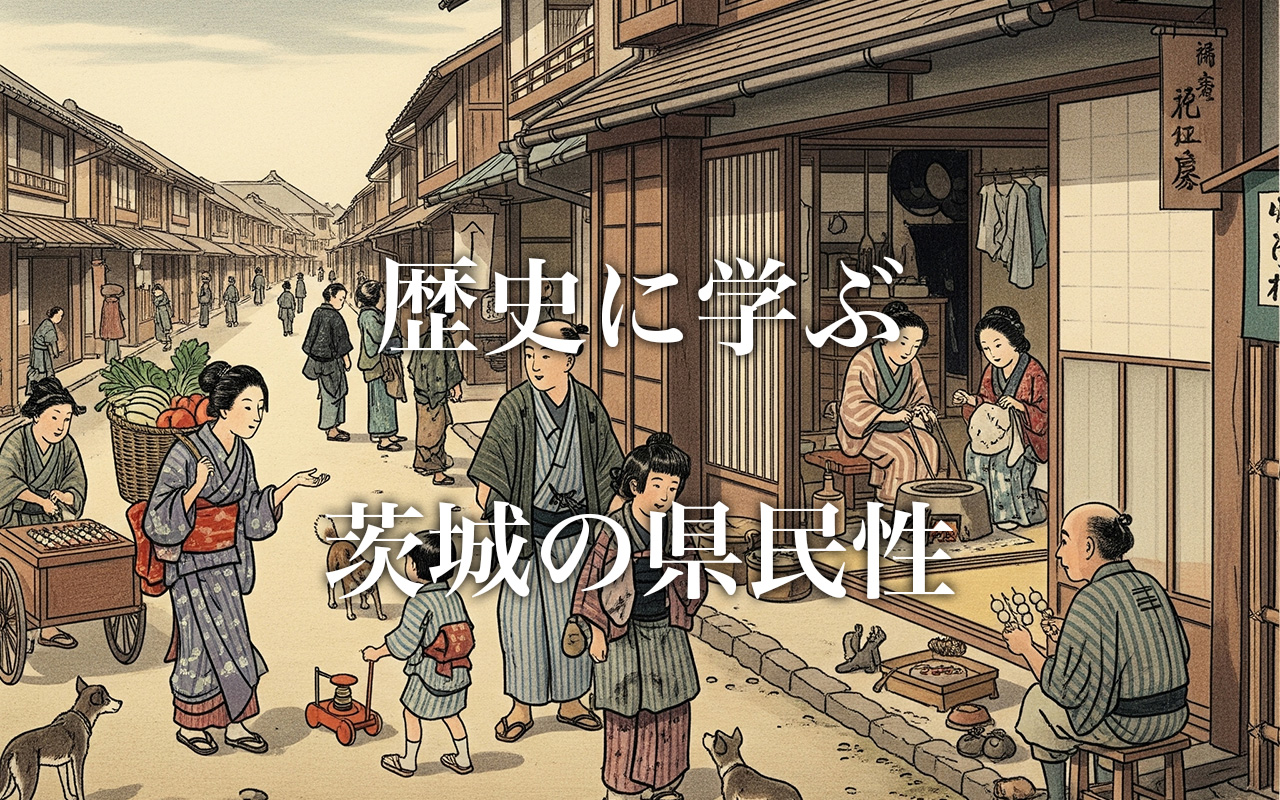


コメント