人は誰しも褒められると嬉しい。批判は、不快だが人を成長させる。だから、僕は批判を真摯に受け入れる。

君は批判されるタイプ・・・
「君は素晴らしい」「その通りだ」と承認されれば、自尊心は満たされ、承認欲求も満たされる。だが、その心地よさに浸りきることは、思考停止に等しいのではないだろうか。
人は批判によってのみ成長する――これは歴史も科学も証明している事実である。
褒め言葉は甘美な蜜のようなものだが、栄養にはならない。逆に批判は苦い薬だが、心を強くし、次の行動を変えるのだ。
批判こそが人類を進化させた

生物学的に見ても、批判や異論は人類進化の原動力であった。

・・・そうなの?
狩猟採集の時代、「この獲物はこう狩るべきだ」と意見を出す者に対し、「その方法では獲れない」と批判する者がいたはずだ。そして、その衝突から新しい狩猟法が生まれ、群れは生き延びたのである。
ダーウィンの進化論を持ち出すまでもなく、自然界に「褒め合うだけの種」は存在しない。競争と批判こそが生存の条件だったのだ。
歴史に学ぶ「批判の力」
日本の歴史を見れば、徳川の繁栄と豊臣の衰退に現れている。

・・・
徳川家康は、自分への批判であっても、家臣の意見を冷静に聞き入れ、計画を修正していたのだ。多様な視点を取り入れることで、より堅牢な権力を手に入れたのだ。
一方、豊臣秀吉は晩年に批判する者を遠ざけた結果、朝鮮出兵という大失策に走った。批判を失った権力者は、必ず衰退する。
学問も異端から生まれた
ガリレオは教会から批判され、ダーウィンは学界から嘲笑された。それでも異端の声が後に真理となった。

批判は科学を加速させる
もし褒め合いしか存在しない社会であれば、人類はいまだに天動説を信じていたに違いない。
脳科学が語る「批判の効能」

神経科学によれば、人間の脳は「快」よりも「不快」を強く記憶する仕組みを持つ。
親に叱られた経験を鮮明に覚えているのは、脳が生存のために「批判」を優先するからだ。
つまり、批判は脳に刻まれやすく、成長につながる最適な刺激なのである。褒め言葉はすぐに消えるが、批判は人格を作る。
傷を舐め合う関係の危険性
現代は「共感で癒されるコミュニティ」が正義だとされている。弱さを打ち明ければ「大丈夫だよ」「あなたは悪くない」と返ってくる。

・・・優しい社会
だが、そこに浸りきれば「現状維持」を選ぶ集団になってしまう。企業の中でも「君は、素晴らしい」と互いに褒め合う組織は、時代に取り残され衰退していく。
批判を排除する共同体は、必ず衰退する。これは歴史が示してきた普遍の法則だ。
真の友情とは「批判できる関係」

友情とは、相手を甘やかすことではない。
嫌われるリスクを背負ってでも、誤りを指摘してくれることこそ本当の友情だ。

そんな仲間が必要だ!!
孔子は「過ちて改めざる、是を過ちという」と説いた。批判をくれる友人は、あなたの人生を救う存在なのである。
褒められるより、批判されたい
もちろん、褒められることは心地が良い。僕も出来るなら褒められ続けたい。

褒められたいんだ・・・
でも、その心地の良さが、僕の成長を停滞されるのであれば、受け入れ難い。反対に、批判は、一見、不快に感じるが、指摘をされる点は、自らの弱点であると思えば、有り難いこと。なぜなら、指摘された欠点を潰すことにより、自らの成長の糧になるからだ。
だからこそ、僕はは褒め合いのぬるま湯を拒み、批判を選ぶ。不快なほどの批判こそが、僕を強くする栄養なのである。
(了)
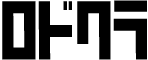




コメント