2025年現在。ふとクルマのことを考えると、1989年・・・日本の自動車産業の転換期について想いを馳せてしまします。
昔の話になってしまいますが、僕の愛車であるNAロードスターの発売が開始された1989年。当時のの熱狂を共有したいと思います。

共感して貰えなくても・・・
僕は、2025年の街で、ユーノスロードスター(NAロードスター)のハンドルを握っていると、ふと1989年のことを思い出します。僕にとって、1989年は、ただの過去ではありません。まるで、日本中が熱に浮かされていたような、光と勢いに包まれた時代の特異点だったような気がしています。

どういうこと?
忘れもしない。当時、中学生だった僕にとって、1989年は「クルマを持つ」という夢が芽生えた年でした。夏休みに、友人の兄が帰省していて、見せてくれたクルマ雑誌の1ページ・・・その現実離れした輝きと、それを語る彼の熱っぽい目が、今でも頭の中に残っています。

僕の原点かも・・・
景気は絶頂で、誰もが「明日はもっと良くなる」と信じてた時代。
カーステレオから流れるシティポップのリズムに合わせて、街も企業も、人の心も、全てがアクセルを踏み込んでいるような・・・そして、そんな空気の中で、日本の自動車メーカーはまるで「世界を変える主役になるんだ」と宣言するように、伝説になるクルマたちを次々と生み出しました。

そうなんだ・・・
あの年、僕の心を一番強く掴んだのは、スペックやスピードじゃなくて、あの時代にしかなかったエレガントで、薄くて、強いデザインでした。
1989年に発表され、いまだに名車として語られるクルマはたくさんありますが、その中でも印象的な3車種について紹介します。
GT-Rの咆哮――“ゴジラ”が生まれた夜の衝撃

1989年の8月。
中学生だった僕は、プール帰りに寄った友達の家で、その『事件』に出会いました。友達の兄が、興奮気味に差し出した分厚いクルマ雑誌の表紙。

・・・中学生
「スカイラインGT-R、復活。」
その文字を見た瞬間、子どもの頃に雑誌で見た「ハコスカGT-R」の記憶と、目の前に現れたR32 GT-Rの姿が頭の中で重なりました。
R32のボディは無駄がなく、削ぎ落とされたようなシルエット。派手さはないけど、内に秘めた自信が滲む「無骨な美しさ」がありました。あの頃のどのクルマとも違う、まるで精密な兵器みたいな緊張感が漂っていたんです。

見るからに・・・
そして、その心臓「RB26DETT」。
2.6リッター直6ツインターボ。カタログ上の280馬力なんて、みんな建前だって知ってました。少しエンジンに手を入れれば400馬力、500馬力なんて軽く出る、底なしのポテンシャルを秘めたエンジンです。
でもGT-Rのすごさは、単なるパワーじゃないんですよね。電子制御4WDの「ATTESA E-TS」と、四輪操舵の「HICAS」。

・・・正に『モンスター』
この2つのシステムが連動して、まるでクルマが意思を持っているかのようにコーナーを抜けていく・・・。当時の僕には理屈なんて分からなかったけど、あの乾いた直6の咆哮を聞いた瞬間、全身が震えました。

大袈裟・・・
「これが未来のクルマの音なんだ」と。
その後、GT-Rはサーキットで無敗。JTCで他車を寄せつけず、「ゴジラ」の異名を手にしました。GT-Rはまさに時代の象徴です。いつかあのシフトノブを握って、首都高を走る・・・そんな夢を、あのエンジン音が僕の中に刻んでいきました。
ロードスターの微笑み――風を取り戻した純粋さ

GT-Rが登場してから、ほんの1ヶ月後の9月。ハイパワーの熱狂が冷めやらぬ中で、まったく逆方向から現れたのが、僕にとって特別な一台・・・ユーノス・ロードスターでした。

衝撃的な可愛さ・・・

スポーツカーなのにね・・・
カーグラフィック誌で初めて見た時、正直、少し戸惑いました。時代は電子制御やターボ全盛。そんな中で、マツダが出したのは1.6リッターの小さなオープンカー。派手な装備もなく、スペック的には地味。
ロードスターが発表されたときは、酷評だらけでした。パワーがないとか、非力なエンジンだとか・・・なんちゃってスポーツカーや、究極のナンパカーなどとも言われていました。

・・・散々だね

時代的に・・・
ですが、ロードスターが提供したのは「走ることそのものの喜び」でした。風を浴びて、エンジンの鼓動を感じて、ステアリングを通して路面を読む・・・それはもう、スポーツそのものでした。
バブルの熱狂が高級志向に偏っていた中で、マツダは「軽さ」と「純粋さ」に立ち返った。それはまるで、馬力至上主義のクルマ文化へのアンチテーゼのように感じました。
そして今、僕はこのNAロードスターのステアリングを握りながら、あの頃に夢見た「走る喜び」を、自分の手で確かめています。
セルシオの沈黙――高級の定義を変えたV8

GT-Rの咆哮、ロードスターの風。そして10月、トヨタは静けさで世界を驚かせました。それが、セルシオの登場です。

伝説の高級車
ただの「トヨタの高級車」じゃなかった。クラウンの上位という枠を超えて、まったく新しい領域に踏み込みました。アメリカでは「レクサスLS400」として発売され、その一台が「日本の高級車」という言葉の意味を塗り替えました。

そうなんだ・・・
セルシオの走りは、ただ静かなだけじゃない。
絶対的な静寂。V8の滑らかさと、キャビンの穏やかさ。ドアを閉めた時の「パスッ」という音まで計算され尽くされていて、それだけで世界の高級車ブランドたちが、ざわつきました。
アメリカでは大絶賛。「静けさ」と「心地よさ」で勝負したトヨタが、メルセデスやBMWを上回る評価を得た瞬間、日本が世界の一線に並んだと誰もが感じました。

・・・そんなに?!
僕たちは、まだ子どもだったけど、ニュースでレクサスの成功を知った時、胸の奥に誇りのようなものが湧きました。セルシオは、ただのクルマじゃない。それは「日本の技術が世界を変えた証」だったんです。
実際に、大学生になり、知り合いの父が所有するセルシオに乗った時に「すごいクルマだ」と実感しました。
1989年という夢のシンフォニー

あの頃の街には、本当に熱がありました。誰もが、明日はもっと良くなると思ってたような気がします。新車の香りが夜風に混じり、未来がすぐそこにあるように感じていました。
それぞれまったく違う方向を向きながらも、三つの音色が一つの旋律を奏でていました。
「日本が、世界の中心に立つ」というメロディです。

ちょっと詩的・・・
1989年に登場したこの三台は、ただの工業製品ではありません。日本のクルマが世界を席巻したのです。
そして今、僕はこのロードスターを走らせながら思います。あの時代のエンジンの鼓動は、まだ僕の中で生きていると・・・。
きっとGT-Rやセルシオのオーナーの方たちも、同じように特別な時代の記憶を胸に抱いてるんじゃないでしょうか。
僕のロードスターは、その記憶を運ぶ小さなタイムマシンなんです。
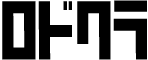



コメント