僕の青春時代であった平成初期。当時の若者は『車は男のステータス』とばかりに、車を手に入れることに躍起になっていた。

車がなければ・・・
街の夜は薄く霞み、街灯の黄色い光が舗道を照らす。その中に停まる車は、ただの移動手段ではなかった。若者たちにとって車は、夢であり誇りであり、自由の象徴だった。
アルバイト代をはたき、古びた中古車を磨き、改造し、首都高や郊外の峠を駆け抜ける。時には借金さえも恐れず、命の一部を削って手に入れた愛車。その姿は、単なる贅沢ではなく、青春そのものの象徴であった。

そんな時代だったね・・・
現代では車を買うことが「贅沢」と呼ばれるが、かつての若者たちにとって車は、夢と生きる力の証であったのだ。
街と車の記憶:車は若者の夢だった

昭和の終わり頃、街の夜は薄く霞んでいた。街灯の黄色い光が舗道を照らし、車のヘッドライトが暗闇を切り裂く。若者たちにとって、車は単なる移動手段ではなく、自由と希望の象徴であった。
僕らの世代では、スカイライン、Z、シビック、RX-7・・・若者が憧れる車がたくさんあった。中古であっても、磨き上げ、カスタマイズすれば自分だけの一台になる。週末には首都高や郊外の峠に車を走らせ、夜の街の風景と一体化する感覚を楽しんだ。

個性が強い車たち・・・
「見ろよ。俺の車だぜ。」
友人の声には誇らしさが溢れ、古いセダンもどこか輝いて見えた。その背後には、夜風に揺れる街路樹が長く影を落としていた。
大学生の僕は初めて自分の車のキーを握った時、胸が高鳴った。アルバイト代をはたき、古い車を改造し、休日には夜の街を駆け抜けた。車を買うことは生活を超えた贅沢であり、青春そのものだった。
車はただの道具ではない:中古車文化の魅力

車は工業製品に過ぎない。洗濯機や冷蔵庫と同じく、生活を便利にする道具である。しかし、若者にとって車は道具以上の価値を持った。夜の街を走る車は、自由と夢を映す鏡であった。

車が欲しかった・・・
1980年代~1990年代は、中古車の市場が拡大し、学生でも手が届く車が増えていた。たとえば、ホンダ・シビックやトヨタ・スターレットは10万~30万円台で購入でき、改造パーツも豊富であった。若者は磨き、改造し、自分だけの一台を作る楽しみを覚えた。

手に入る価格・・・
峠や首都高での走行も、ただ移動するためではなく、車を手に入れる喜びの延長であった。エンジン音が夜の街に響くとき、青春の鼓動と街の灯りが重なった。
無理をしてでも車を買う心理:若者の車購入動機

贅沢とは、生活に必要なものを超えた消費である。借金をして車を手に入れることは贅沢であった。しかし、多くの若者は夢を追い、命を削って働いた。

・・・そこまで?!
「いつかは大きくなってやる」
首都高でエンジンを唸らせる音は、若者の心の鼓動でもあった。中古車でも、手に入れるための努力と時間が、車を特別なものにしたのである。

車は男のステータス
統計によれば、1990年代の若者(20代前半)の自動車保有率は約35%。今と比べると低いが、それでも若者たちは必死に車を手に入れていた。
月々の維持費(保険・ガソリン・車検・駐車場)は平均3~5万円。学生や若手社会人にとって決して小さくない負担である。
贅沢は若者の正義:ファミリーカー事情と維持費
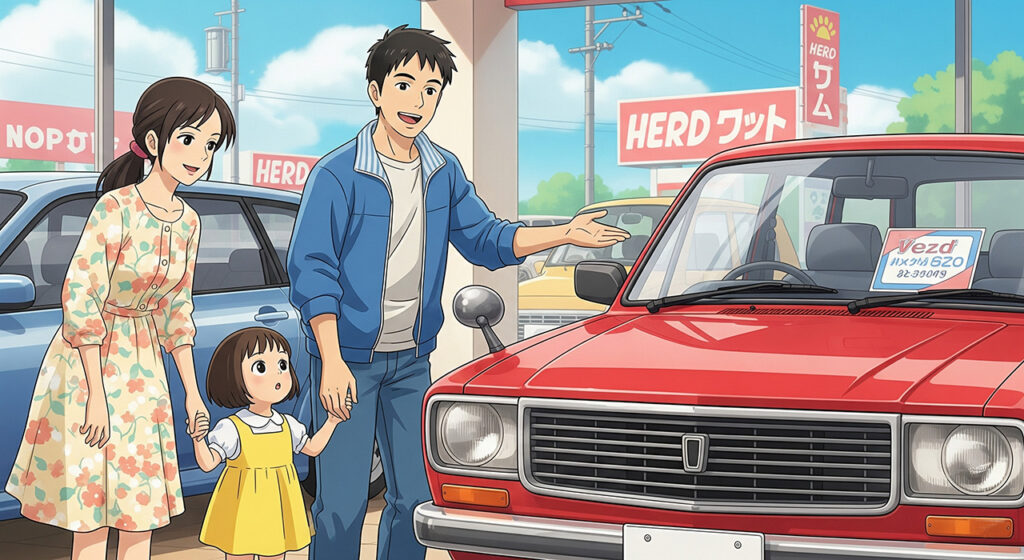
現代では、車を買うことは合理性や費用対効果の観点から「贅沢」と見なされる。しかし、あの時代の若者たちは全力で車を手に入れた。維持費も惜しまず、燃料や保険に苦心しながら夢を諦めなかった。
確かに、現代の車は高価になった。でも、当時の若者はそれでも、車を手に入れようとした。それは、家族を運ぶために必要不可欠だからだ。
時代は流れ、当時スポーツカーに熱狂した若者も、家族想いの優しい父親世代になったのである。
現代への眼差し:なぜ車は再び贅沢になったのか
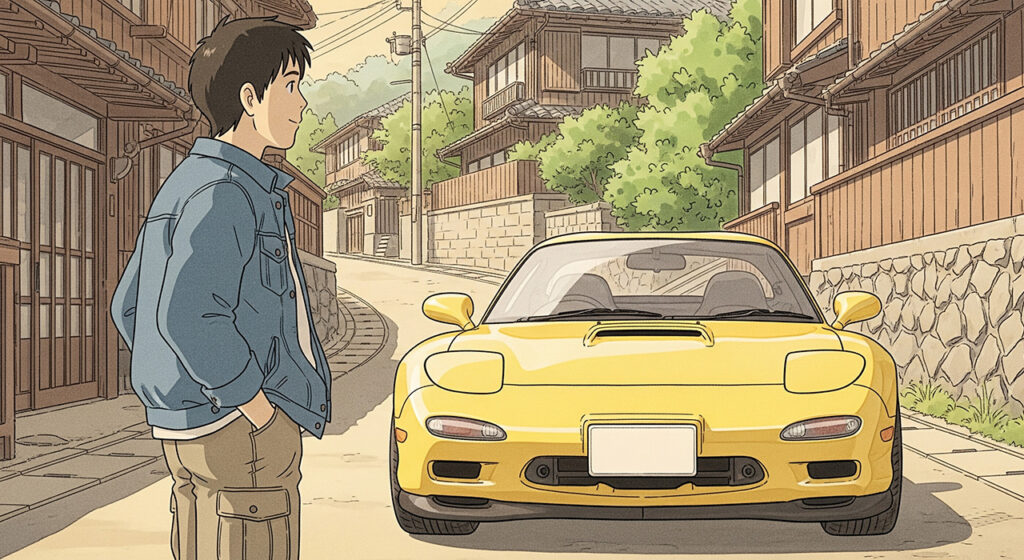
現代の若者は、車を購入する夢を持つ人が少ない。合理性を重視し、維持費や燃費、保険料を計算する。中古車市場も整備され価格は以前より安くなったが、「必死に手に入れる贅沢」という感覚は薄れた。
しかし、欲しいもののために必死になる心、夢を追う力は、いまだ人生を輝かせる原動力である。
車を買うことは、単なる贅沢ではなく、生きる力の象徴なのだ。
もちろん、昭和的な古い価値観であることは否めない。でも、贅沢は悪だという考えには賛同できないのである。
(了)
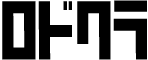


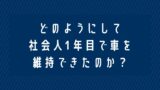





コメント