「氷河期世代って優秀だよね」。最近、そう言われることが増えた気がする。
なんだか、こそばゆいような、でも「そうだろう?」と心の中で不敵に笑うような、複雑な気持ちになる。
無理もないと僕は思う。なぜなら、僕たちは、この言葉が持つ「優秀さ」の定義を、文字通りその身をもって書き換えてきた世代だからだ。

我々は優秀だ!!
学歴、成績、真面目さ、努力。
社会に出るまでは誰もが信じて疑わなかった「優秀さ」という名のパスポートを片手に、社会の分厚い扉を叩いた。しかし、そこで待ち受けていたのは、パスポートすら受け取ってもらえない理不尽な現実だった。

過酷な時代だった・・・
この記事では、そんな時代をサバイブしてきた俺たち氷河期世代が、いかにして「優秀」と呼ばれるようになったのか、そしてその背景に何があったのかを、赤裸々に語っていこうと思う。

聞こうじゃないかっ!!
始まりは、理不尽の代名詞「就職氷河期」

俺たちが新卒で社会に出た1993年〜2005年頃。当時は、求人倍率が0.5前後という異常事態だった。これはつまり、「働きたいと願う人間が2人いるとして、正社員になれるのは1人だけ」ということ。

すごい時代・・・
今思えば、狂気の沙汰だ。
大学の成績は常にトップだった友人が、十数社受けても書類すら通らない。学歴は申し分ないはずなのに、なぜか大手企業には面接すら呼んでもらえない。「内定ゼロ」で卒業し、コンビニや派遣のバイトを転々としながら、次の一手を模索する日々・・・。
その姿を見て、僕は「この社会は、僕たちの能力を正当に評価する気がないんだ」と悟った。

うむ。分かる!!
幸い、僕はなんとか内定をもらうことができた。周囲からは「勝ち組」だと称賛されたが、正直なところ、そんな言葉はむなしく響くだけだった。
なぜなら、その内定は俺の能力や努力の正当な評価ではなく、ただ単に運が良かっただけだと知っていたからだ。

運だけである
当時を生きた人間なら、この感覚は痛いほどわかるはずだ。どれだけ真面目に、誠実に努力を重ねても、報われるとは限らない。むしろ、報われないことの方が圧倒的に多い。
「優秀なのに、社会から居場所を奪われた人」は、俺たちの周りにいくらでもいた。
俺たちは、そんな不条理な現実に真っ向から立ち向かうしかなかった。
僕を鍛え上げた「地獄の労働環境」
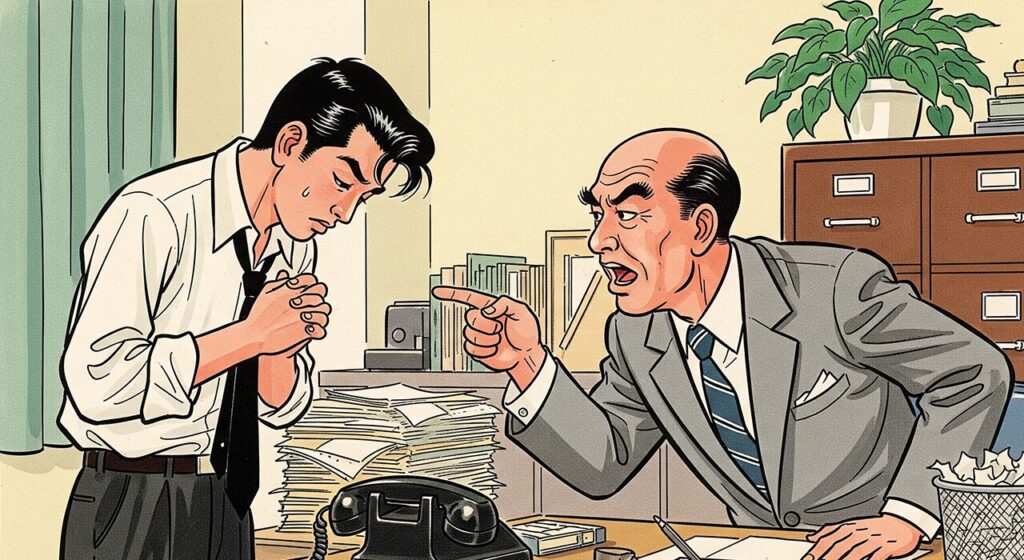
なんとか社会に出ることができた僕を待っていたのは、就職活動に勝るとも劣らない「地獄」だった。
今考えれば、入社した会社は、今でいう「ブラック企業」の典型例だったと思う。定時という概念はなく、日付が変わってから帰るのは日常茶飯事。残業時間は毎月100時間を超えるのが当たり前で、上司からは「嫌なら辞めろ」と毎日のように言われた。

・・・つらかったね
もちろん、パワハラなんて言葉は存在しない。理不尽な要求に耐え、ただひたすら歯を食いしばって働くことが、美徳とされていた時代だ。
「若いんだから、寝る間を惜しんで働け」
「俺たちの頃はもっと大変だった」
「お前は、この会社の役に立っているのか?」
そんな言葉を浴びせられながら、僕たちは必死で食らいついた。しかし、その環境は誰にとっても平等ではなかった。

必死だった・・・
同期のなかでも特に真面目で、責任感が強く、優秀な奴ほど精神的に追い詰められ、次々と会社を去っていった。まるで「誠実さ」や「責任感」が、この時代を生き抜くための足かせになってしまったかのように。
一方で、僕は「どうすれば、この地獄を生き抜けるか」としか考えていなかった。目の前の理不尽な要求をどうすれば効率よくこなせるか、上司の機嫌を損ねずに仕事を円滑に進めるにはどうすればいいか・・・。

要領よく・・・
当時の僕は、自分の中にある「優秀さ」の定義を、根本から見つめ直した。。学歴や成績といった「学校的な優秀さ」ではなく、よりタフで、現実的な「サバイブ力」を持つ人間の方が優秀なのではないか・・・。
そしてそのサバイブ力こそが、今の僕の強みとなっている。
生き残るために身につけた、したたかな「優秀さ」
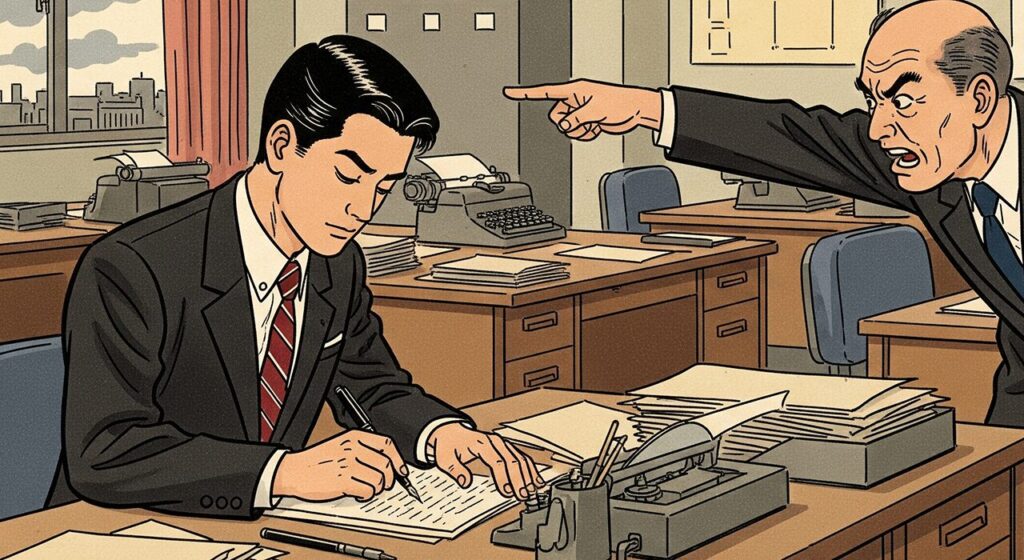
僕たちの世代を観察していると、成功した人とそうでない人の差は、純粋な「優秀さ」ではないと気づいた。

どういうこと?
例えば、俺の友人の一人は、大学時代からトップクラスの成績で、何事にも真面目に取り組むタイプだった。しかし、新卒で入った会社で上司からの理不尽な要求に耐えきれず、わずか3年でうつ病になり退職。
それ以来、不安定な働き方を余儀なくされている。
一方、別の友人は「とりあえず目の前の仕事を終わらせればいい」と割り切る、ある意味で適当なタイプだった。必要以上の責任は背負わず、効率を最優先で立ち回り、プライベートもきっちり確保する。
周囲からは「あの人、あまり仕事に熱心じゃないよね」と陰口を叩かれていたが、結果的に彼は、激務に追われることなく、着実にキャリアを積み重ね、今では大手企業の管理職を務めている。
この対比が示すのは、俺たちの世代が生き残るために必要だったのは、単なる「優秀さ」ではないということだ。
それは、不条理な現実を冷静に受け止め、自分なりの折り合いをつけ、前に進む「したたかさ」であり、「適応力」だった。
その力こそが、僕たち世代の人間を「優秀な人材」へと押し上げたのだ。
氷河期世代が今、改めて評価される理由
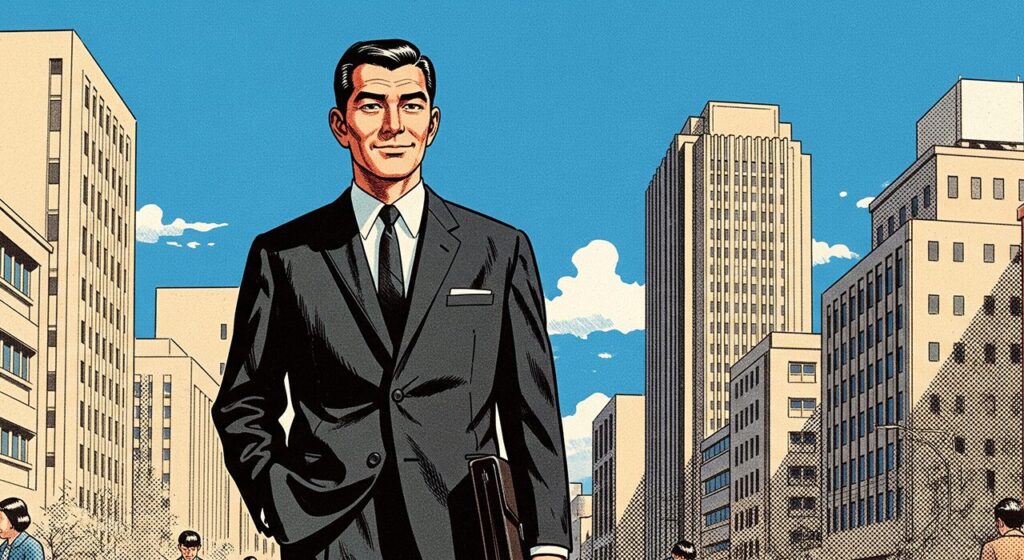
そんな不遇の時代を生き抜いてきた僕たちが、今、改めて社会から「優秀だ」と言われ始めている。
その背景には、僕たちの世代が持つ、いくつかの圧倒的な強みがある。
1. 圧倒的な「理不尽耐性」
俺たちは、ブラック企業で鍛え抜かれた。理不尽な要求、徹夜での作業、パワハラまがいの叱責・・・。
それらを全て経験してきた僕たちにとって、現代社会で起こるちょっとしたトラブルなど、些細なことだ。まるで、極寒の地を裸足で歩いてきた人間が、真夏のアスファルトを歩くようなものだ。
僕たち世代のタフさは、今の若手世代とは比べ物にならない。
2. 現実的な「問題解決能力」
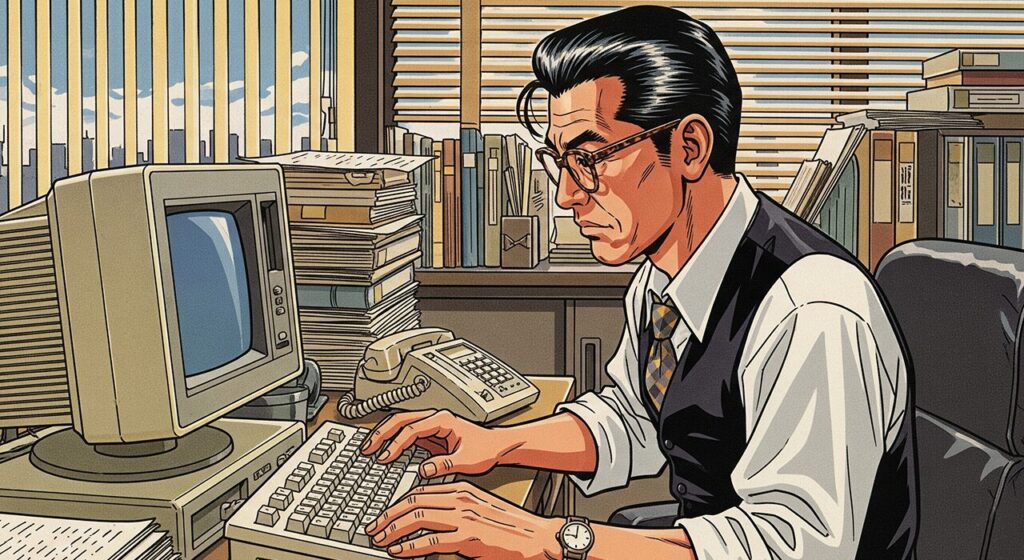
僕たちの時代、正論は通用しなかった。
「正しいかどうか」ではなく、「どうやってこの状況を切り抜けるか」が常に問われていた。だからこそ、僕たちは理想論を語るのではなく、現実的な落としどころを探し、実行する能力に長けている。
このスキルは、ビジネスにおいて非常に重要であり、僕たちが管理職やリーダーとして活躍できる大きな理由の一つだ。
3. キャリアを自分で切り拓いてきた「柔軟性」
新卒で正社員になれず、派遣や非正規、フリーランスなど、多様な働き方を経験してきた仲間も多い。その経験は、ひとつの組織や働き方に固執しない「柔軟性」を与えてくれた。
会社員から独立し、再び会社に再就職する。そんなキャリアチェンジも当たり前だ。
「この会社が全てではない」
「この働き方が唯一の正解ではない」
そう知っているからこそ、僕たちはどんな環境にも順応し、自分の居場所を見つけることができるのだ。
俺たちの「優秀さ」は、学歴や成績では測れない
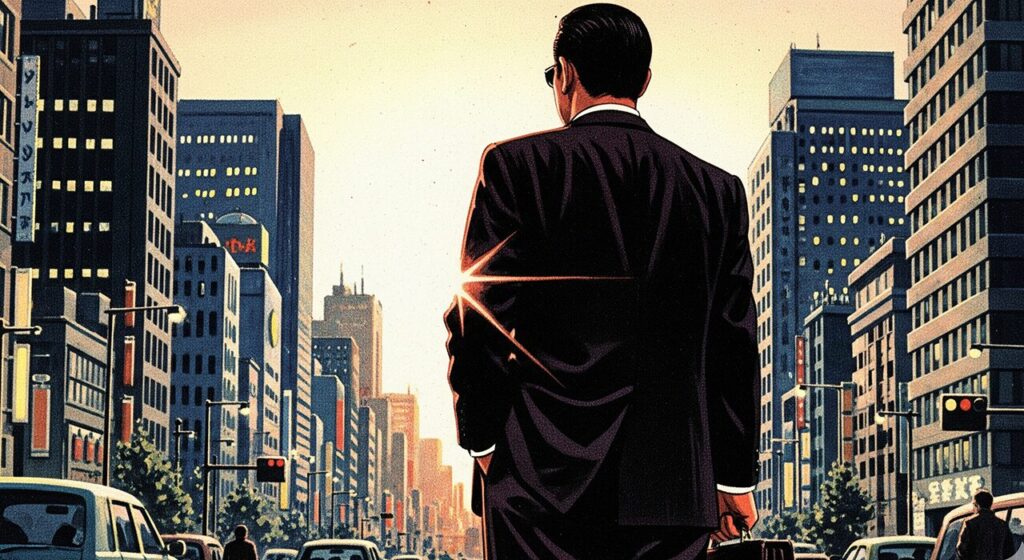
結論から言おう。氷河期世代の「優秀さ」は、決して学歴や成績といった、わかりやすい指標で測れるものではない。
それは、不運や理不尽を真正面から受け止めながらも、自らの手で未来を切り拓いてきた「サバイブ力」であり、どんな環境にも適応し、したたかに生き抜く「人間力」だ。
僕たちは、誰かに与えられたレールの上を歩くのではなく、泥臭く、自らの力で道なき道を切り拓いてきた。
その過程で身につけた経験、忍耐力、そして現実を生き抜く力こそが、今の時代に最も求められている「優秀さ」なのだと信じている。
だからこそ、胸を張って言おう。
僕たち就職氷河期世代は、本当に優秀だ。
そして、それは運良く与えられたものではなく、自らの努力と経験によって勝ち取った、紛れもない真実なのだ。
(了)
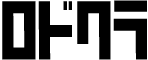
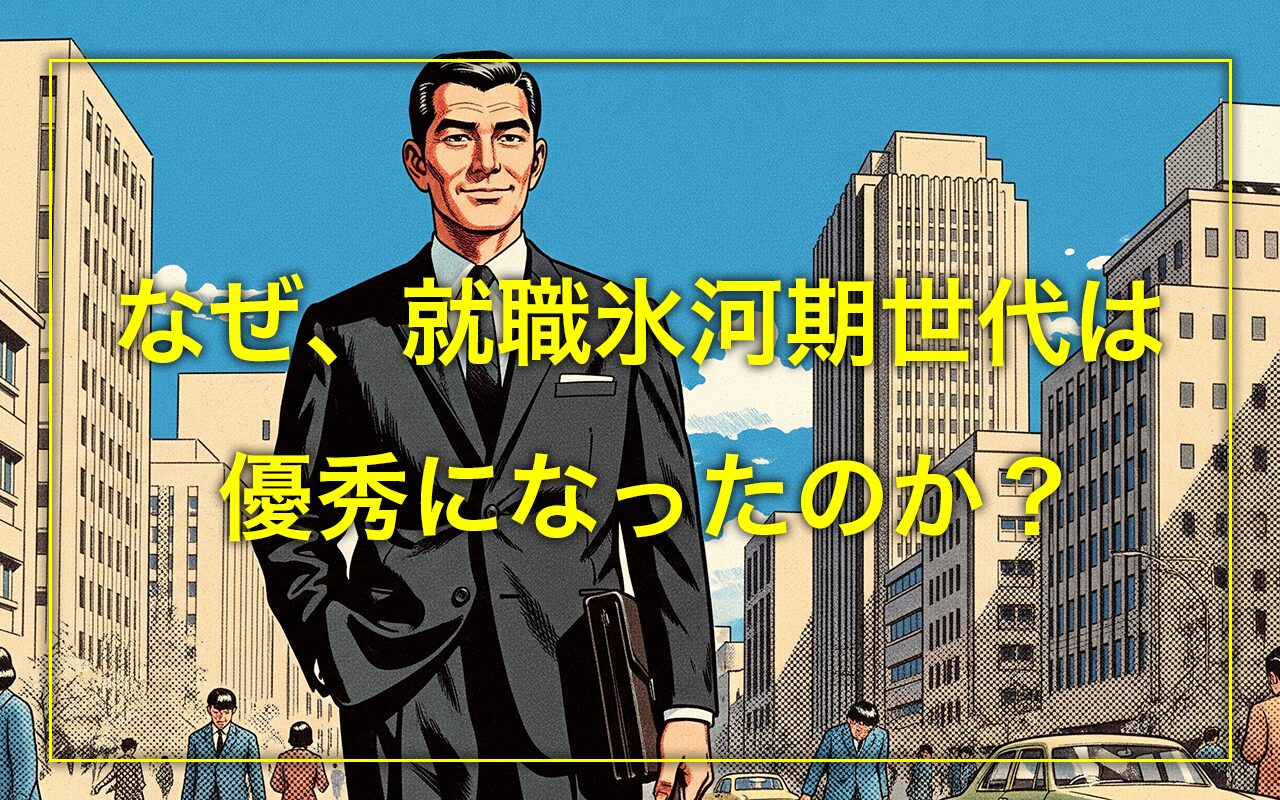


コメント